| No. | 本 | 読後感 | |
|---|---|---|---|
| - | w041 |
「自分を動かす名言」 |
|
| - | w040 |
「もう一度花咲かせよう」 |
一生懸命書いたであろう原稿が、シュレッダーに消えていく――費やした時間は何だったのか。虚しく感じるも、人生とはそんなものか……。
|
| - | w039 |
「書く全技術」 |
340ページ余りの最後に、書きながら世界を広げていけることが記されている。――書くことは、自分の世界が広がるということだ。
|
| - | w038 |
「働きながら書く人の文章教室」 |
町工場の旋盤工を経て文筆業となった著者。生涯のテーマを「人はなぜ働くのか」にしたという。本の中で紹介している「阿久津のじいさん」は、人間の生きざまを感じさせてくれる。
|
| - | w037 |
「こころとお話のゆくえ」河合隼雄
|
河合隼雄さんが審査員を務めた「児童文学ファンタジー大賞」第3回選考委員会のことが書かれていた。「作品」に対する期待値の高さが記述されている。「文学作品」は、やはり読むも書くも縁遠い世界だ、また一歩、距離を置くことになった。
|
| - | w036 |
「言葉を遊弋させる」
|
「言葉を遊弋(ゆうよく)させる」という表現が、「人生はいつもちぐはぐ」(鷲田 清一)に記されていた。言葉を伸び伸びと繰る印象を受ける。言葉を遊弋させていた時期と大学総長になってからの状況を引用する。
|
| - | w035 |
工学部ヒラノ教授とおもいでの弁当箱
|
工学部の語り部を標榜する著者が、〝もの書き〟に必要なものは、〝分析力、編集力、虚言力〟の三つである、と述べている。
|
| - | w034 |
戦争
|
戦争体験というと悲惨な場面を思い浮かべるが、ここでは子どものときの戦争体験が書かれている。子ども視点での日常生活の描き方が上手だと思う。擬態語を使った表現も参考になる。
|
| - | w033 |
「老いを忘れさせるもの」
|
<引用>
|
| - | w032 |
|
|
| - | w031 |
「作家の収入」
|
小説を書くこと=仕事、と割り切って成功した著者。ここまで内幕を開示してしまうのかと驚いた本。
|
| - | w030 |
日経新聞コラム
|
<引用>
|
| - | w029 |
日経新聞コラム
|
<引用>
|
| - | w028 | 「もっと読みたい」と思わせる文章を書く
加藤 明 |
<引用> エッセイの手ほどきをしていて、気がついたことがあります。 みなさん、「自分の書いた文章は、だれもが最後まで読んでくれるもの」と思い込んでいらっしゃることです。この際、はっきり申し上げておきましょう。 あなたがお書きになった文章は、家族や親しい友人ならともかく、赤の他人はほとんど関心が ありません。 あなただって、名の知れた作家やエッセイストならいざしらず、ふつうの人が書いた文章にあまり興味をもてないというのが本音ではないでしょうか。人間なんて、そんなものです。 作文とエッセイの違い 作文 書き手が主役の世界 エッセイ 読み手が主役の世界 |
| - | w027 | 人それぞれの轍(新聞掲載エッセイ)
宮田 珠己 |
<引用> やってることがあまりにマイナーなせいか、 「そんなことで食べていけるのか」 「いつまでもそんなこと続けてて大丈夫?」 「お父さん、どうしてうちってお金ないの?」 などと心配されるが、そういうものしか書けないんだから仕方がない。私だって、もっと売れそうな実用的な本が書けるものなら書きたい のだ。 20年間物書き生活をやってきてわかったことのひとつは、人の人生にはそれぞれの轍のようなものがある、ということだ。 どろんこ道に、地面をがっぽりとえぐって続く車の轍。 できることなら、道路の好きなところを自由に転がっていきたいんだけれども、気がつけばはまりこんでいる轍。誰に強制されたわけでもな いのに、どうしてもそこを走ってしまう轍。 ・・・ 実に詮無き話だけれども、最近は、だんだんこの轍こそが私なのだと思うようになってきた。その轍が自分オリジナルの形を作っているのだ。 |
| - | W026 | 思い通りにいかないから人生は面白い
曽野綾子 |
駄作について、作家としての心のうちを描いていて面白い。 <引用> このごろは、部分的にあきらめることもできるようになってきました。前は、駄作を書く と猛烈につらかったのですが、今はあまりつらくない。「そうだ、人間というのは駄作も書くもん だ」と思うようになりました。 いっとき私は、たくさん書き過ぎるから駄作を書くようになるんだ、と思ったんです。です から十本の短篇を書くのをやめて、一本だけにすればいいのかしらね、と言ったんです。そうし たら、三浦朱門が笑って「なあに、九本の駄作を書くから、ややましな一本が書けるのさ」と 言うんです。確かにそういう面もあるんですね。 その時によるのですが、編集者に「あんな駄作を渡しちゃって、ごめんなさいね」と言っ てもいいですしね。そう言ったらお互いが気まずくなると思ったら、名作を渡したような顔をし ている。黙っていればいいんです。 人はそれくらいの形で相手をだましてもいいと思いますよ。駄作を読んだからって、下 痢をするというものでもないでしょう。そういうふうに考えるんです。 心の内まで平気なわけではありませんよ。そういう時には、しおれているわけです。 でも、そのうち時間が経つと、失敗したことを忘れて、またもう一度やってみよう、と思うように なる。それも芸のうちでしょうね。 そして、心の中のどこかで、ああ、悪いことをしたから、もし今度あそこで書かせてもらう ことになったら、いい作品を書かなければいけないな、と一応思っているんですね。思っていて、 その次も駄作になるかもしれませんけれど。 |
| - | w025 | 文章力の鍛え方
樋口裕一 |
韓流ドラマ「冬のソナタ」は、基本的には三つのテクニックを駆使してつくられていると いう説明があった。 <引用> まず視聴者が気づいてしまうのです。「この二人はどうも兄妹なんじゃないか」「いや、 兄妹ではなさそうだ」といった疑問を持たせます。2話、3話になって、やっと登場人物たちが 気がつくわけですが、この「2、3話あと」というのが絶妙のポイントで、視聴者はいじらしくて しょうがなくなるのです。 (略) この「焦らす手法」を終始やり続けると、視聴者は「なんで気づかないの病」にかかる のです。本当はここで気づくはずなのに、わざと気づかせないといったテクニックも必然的に混 じってきますから、視聴者は歯がゆくてしょうがない。これで恐ろしいくらいに感情移入してしま うというのが、一つ目のテクニックです。 二つ目のテクニックは、「運命にしてしまう手法」です。そうそうないような話が、次から 次へと起きても、視聴者は「そんなバカな」と素直に思わされてしまうのです。 普通ならしらけてしまうことでも、そう思わせない工夫として、星占いやタロット占いで 「この二人は出会う運命だったんだ」というようなことがときどき出てきます。そうすると不思議 なことに、見ている側は「ああ、運命なんだ」と思ってしまうのです。 このしかけがなければ、「いくらなんでも、そんな偶然はないだろう」としらけてしまうところ を、「運命だ」のひと言で納得させてしまうわけです。これは、使い方をよく考えて仕込むと意 外と効果があります。 三つ目のテクニックは、「音楽と映像でイメージをオーバーラップさせる手法」です。「二 人がバスの中で会って愛を交わしたあと、雪の中を自転車に乗って……」というシーンで、BGM にワーグナーの「婚礼の合唱」を挿入します。そのシーンが、音楽つきで流れると、視聴者は ジーンとするのです。ある種、条件反射みたいなものですが、そんなシーンを5、6個用意し、 その情景を「ああ、あのとき」と思い出させるようにときどき織り交ぜていくと、視聴者は釘づけ になります。 |
| - | w024 | 一夜漬け文章教室
宮部修 |
本からの引用:
ダメな傾向③;わかり切った一般論の展開 だれもが知っている一般論を並べたてる傾向は、平凡でだれもが共通の思い をいだきやすい課題のときに出る。例えば「友人」「恩師」「親」「読書」「休日」 などである。 「趣味」が課題だとすると、学生たちは野球、サッカー、音楽、映画、書道、 デザインなど自分の好きなことのメリットを解説してくれる。ありふれた例として、 自分は小学校からサッカーをやっていて、運動をしない友人よりも体力があり、友 だちの輪も広い、将来はイギリスのプロチームに入って活躍したいと夢を語る。 趣味のない学生は、一般論的な趣味論を書く。「趣味はそれぞれの人の価値観、 考え方、性格により異なってくる。でも生きていくうえで、とても必要なものである。 音楽鑑賞が好きな人は、音楽を聴くことで安らぎを得てストレスを発散できる」。 このような具合である。 これを読むと、「その通りですネ」と同感するだけで、何もコメントできない。 読後になんの共感も残らないからだ |
| - | w023 | 大阪ばかぼんど
黒川博行 |
本からの引用:
わたしは小説のプロットを考えるとき、七転八倒する。トイレや散歩や 夢のお告げでヒントを思いつく――そんなものは大嘘で、わたしは部屋に閉じ こもり、ヒイヒイうめきながら考える。 プロットができあがると、資料を集め、取材をする。取材の相手は初対 面の人がほとんどだから、当然のごとく警戒される。こちらの趣旨を理解して もらって、おもしろい裏話を聞くには、さきに資料を読みこなして、その業界 の基本知識を頭に入れておかなければならず、これはけっこう骨が折れる。 そんなふうにして、ようやく原稿を書きはじめたら、やれキャラクター が気に入らない、場面設定にリアリティーがない、せりふがクサい、アクショ ンが足りない、読者が退屈する、とアラが目についてきて、そうなればもう前 に進めず、もとにもどって一から書き直すから、効率がわるいことおびただし い。時間をかけたからよい作品になるというような手前勝手な思い込みはして いないが、ひとつつまずくと、どうしてもその場に停滞してしまう。 「あんたはほんまに書くのが遅い。鼻毛なんか抜いてんと、さっさと仕事し」 よめはんがよくいう。 「おれはな、鶴が一本、一本、羽根を織り込むように書いていくんや」 なんと、文学的な表現ではございませんか。 「ヘーえ、ものはいいようやね」 よめはんは大きな頭を横に振って、こういった。「いい案がある。わたし が口述して、あんたがワープロを打つねん」 |
| - | w022 | 思い通りにいかないから人生は面白い
曽野綾子 |
本からの引用:
このごろは、部分的にあきらめることもできるようになってきました。 前は、駄作を書くと猛烈につらかったのですが、今はあまりつらくない。 「そうだ、人間というのは駄作も書くもんだ」と思うようになりました。 いっとき私は、たくさん書き過ぎるから駄作を書くようになるんだ、と 思ったんです。ですから十本の短篇を書くのをやめて、一本だけにすればいい のかしらね、と言ったんです。そうしたら、三浦朱門が笑って「なあに、九本 の駄作を書くから、ややましな一本が書けるのさ」と言うんです。確かにそう いう面もあるんですね。 その時によるのですが、編集者に「あんな駄作を渡しちゃって、ごめん なさいね」と言ってもいいですしね。そう言ったらお互いが気まずくなると思 ったら、名作を渡したような顔をしている。黙っていればいいんです。 人はそれくらいの形で相手をだましてもいいと思いますよ。駄作を読ん だからって、下痢をするというものでもないでしょう。そういうふうに考える んです。 心の内まで平気なわけではありませんよ。そういう時には、しおれてい るわけです。でも、そのうち時間が経つと、失敗したことを忘れて、またもう 一度やってみよう、と思うようになる。それも芸のうちでしょうね。 そして、心の中のどこかで、ああ、悪いことをしたから、もし今度あそ こで書かせてもらうことになったら、いい作品を書かなければいけないな、と 一応思っているんですね。思っていて、その次も駄作になるかもしれませんけれど。 |
| - | w021 | 特許図面なんかこわくない!!
山田康生 |
本からの引用:
「表現とは、自分を相手につたえるための手段です。表現とは自分だけ の世界ではありません。相手があります。自分だけいいたいほうだいいったか らといって、何の役にもたちません。 その相手が、問題です。人間なんて、もともとがなまけ者です。ひと様 のかいた文章なんか、読むのさえめんどうです。興味をもっている内容でもな い限り、読む気もしません。」 「灰皿の例では、図2に示しました。火のついたタバコが、いままさに落 ちようとしている瞬間を、示しました。のっぴきならない問題点を、うったえ ています。こんなのが、〝ものをいう図面″です。」 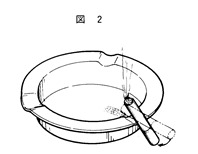
「トレーシングペーパーを使わずに、たとえば白色上質紙に図形をコピー したものでも許されます。このやり方は、安っぼくしあがるおそれがあります。 〝高っぽく″しあげる方法でも見つからない限り、私としてはトレーシングペー パーでやります。」 ――書くことには、図面を書くことも含まれると感じた。著者が、〝もの をいう図面″をきっちり書くことを信条としていることが伝わってくる。 |
| - | w020 | 評論家入門
小谷野敦 |
本からの引用:
数学や物理学なら、ある限定された知識に基づいて何らかの結論を引き出 すことができる。ところが、こと文藝評論とか人文学評論で、ちょっとしたこと を言おうとすると、知識量がものを言う。つまり、知識が大してなくても、基本 的な訓練の上に半年の調査をすれば、近世の随筆の作者について論文は書けるけ れど、仮説を立てようとすれば、知識量が多ければ多いほど微密な仮説、正確な 仮説が立てられるのであり、そもそもこの世に、古今東西のあらゆる文書を読ん だ人などいないのだから、知識の乏しい人の仮説より、知識の多い人の仮説のほ うが正確、厳密になる。これは当然のことだ。 ――文藝評論家が書いたものを読むと、別世界の細々した「事実」や価値観をも とに、作品を批評(攻撃)していることが多い。なるほどと思うことはほとんど なく、ウンザリして途中で閉じることになる。 「正確、厳密」なのかもしれないが、素人には理解できない。だから、文 藝評論家の書いたものは避けるようにしている。 |
| - | w019 | 大人のための文章教室
清水義範 |
〈用語の訛り〉に気をつけることが書いてある。
〈用語の訛り〉とは聞きなれない言葉だが、以下に書いてあるようなことだ そうだ。 本からの引用: 二十一世紀になってもまだ、「彼女はパンタロンをはいていた。」と書い ちゃって、お年寄りだなあ、と思われるのは損なのである。今はそれはパンツと いうのが無色の用語なのだ。パンツと書いてあるから下着のことかな、と思う人 はもうそういない。 同じような理由で、ある会社の商品名を一般名称のように使うのもなるべ く避けよう。NHKじゃないんだから、厳密になりすぎることはなくて、テトラポッ ドとか車のポルシェなどにまで神経を尖らせることはない。しかし、宅急便はヤ マト運輸の商標名だから、宅配便と言っておこうとか、サビオも、バンドエイド もやめて、そのことは傷テープと書いておこう、と気配りするのが、〈用語の 訛り〉に気をつけるということである。 |
| - | w018 | [実践]小説教室
根元昌夫 |
著者の解説(以下)で『坊っちゃん』が名作だということがわ
かった。名作は含蓄があるから繰り返して読めるのだろう。
《夏目淑石の『坊っちゃん』にも同じテーマがあります。坊っちゃんにも「坊っちゃんは 正しい」と言い続けた人物がいて、それゆえにあのストーリーがあるのです。 坊っちゃんは松山の中学に赴任した当初、赤シャツというやつはどうも気にくわないと 思っていました。しかしその後、赤シャツから妙に親切にされるうち、赤シャツや野だい こにまるめこまれ、山嵐やうらなりとは背反する形になります。 赤シャツと野だいこ。彼らはある意味で「近代」であり「東京」です。人を組織化した り、利用したり、謀略を使ったりする。人間としては正しくないのですが、政治的、現実 的には勝つ人たちです。 一方の山嵐とうらなりは、「江戸」であり、ある意味「会津」でもあります。そして彼 らは、正しいのに負けてしまうのです。 坊っちゃんは、なぜ正しいほうが負けるのかと憤ります。坊っちゃんは「江戸」なので す。だから最後には、赤シャツ側に鉄槌を加えてやるという行動に出ます。小説というの は、やはり最終的には正しい人に勝ってはしいのです。 坊っちゃんのことを「正しい」と言い続けた人。それは、坊っちゃんに無条件の愛情を 注ぎ続けた清(きよ)でした。清も、それこそ無力で名もなき老人です。》 |
| - | w017 | 書いて稼ぐ技術
永江 朗 |
「フリーライターにとってもっとも大切なのが編集者とのつきあい
です。編集者を信頼しなければなりません。
それはなにも編集者が仕事をくれるからではありません。編集者は企画を一緒 に考え、実現化に向けてともに働くパートナーであり、原稿を読む最初の読者であり、 その原稿についてアドバイスしてくれる助言者です。編集者なしの本も考えられなく はないけれども、クオリティはあまり期待できないでしょう」 ――作品にするなら読者を意識しなければならない。意識しても独り善がりの 自己満足に陥りがち。編集者の必要性ここにあり、ということか。 |
| - | w016 | 小説家という職業
森 博嗣 |
「すベてがFになる」「ジグβは神ですか 」「数奇にして模型 」
――こんなタイトルの本を書く異才。累計で1300万部を超えるベストセラー作家。
従来の作家とは異なる視点が面白い。たとえば、以下。 〈では、何を目指して作るのか? それは大変難しい問題だけれど、あえて一言 でいうならば、「新しさ」である。 今までにないもの、珍しいもの、そういうものを消費者は無意識に求めている。 また、整ったもの、安心して消費できるものは、既に「名作」として膨大な数のストッ クが揃っていることも念頭に置かねばならない。「さらに生産する理由」がどこにある のか、を生産者は常に考える必要があるだろう〉 ――強烈な主張だ。 |
| - | w015 | 60歳で小説家になる
森村誠一 |
「まずは日記に嘘を書く。他人に見せるために美化してもよい。
小説家志望者が、毎日文章を書き続ける訓練として、最も入りやすいのが日記である。 ただ、経験した事実を、正直に書いてはいけない。他人に見せる意識がないと、文体 と文章が甘くなる」 「嘘がうまくなればなるほど、小説を書くためのトレーニングになるのである」 ――お話としての「嘘」、「美化」という技が使えないと他人は面白くないということ だ。ちょっと表現を変えてみることから始めてみようか…。 |
| - | w014 | 心臓外科医である南淵明宏(1958年生)のエッセイ
(新聞コラム) |
心臓外科医という多忙な職にありながら、
「趣味と言えば、モノを書くこと。ブログを書いています」とのこと。
氏のブログは、単刀直入、ズバズバと切りまくる痛快さがある。 これだけ縦横無尽に書ける力があることを羨ましく思う。 |
| - | w013 | わかりやすく伝える技術
藤原慎也 |
クリティカル・シンキングとは、
「適切な基準や根拠に基づく、理論的で、偏りがな
い思考」のことをいうそうだ。ロジックとは、「根拠
(データと論拠)に基づく主張」とのこと。
人にわかってもらうための思考法なので、心がけたい。 |
| - | w012 | やさしい文章表現法
中西一弘 |
著者は、「『なんとも言えない』、『言葉で言い表せない』 は禁句である。適当な言葉に逃げないで、『この言葉こそ』と言えるもの を探し出す。なんとかして、言葉で表す努力をしてみよう」と言う(なるほど)。 |
| - | w011 | 明快な文章
阿部 紘久 |
著者は、「そもそも文章というものは、書き手が一生懸命 あれもこれもと文字を連ねても、そのすべてが読み手に伝わるという保証は 全くありません。読み手にとって理解しやすく、かつ関心を持てる部分、 共感できる部分だけが伝わるのです」と言う(なるほど)。 |
| - | w010 | 日経新聞書評
谷川直子 第49回文藝賞受賞作「おしかくさま」 |
「このまま売れないエッセイストで終わりたくない」 と新人賞に応募し続けたという。1960年生まれでも、新人賞をもらえる のが作家の世界(2012年受賞)。サラリーマンなら肩たたきの世代に入っ てしまうのだが、筆力次第ということなのだろう。 |
| - | w009 | プロを目指す文章術
三田誠広(まさひろ) |
「著者は、『恐怖』という言葉を使わずに恐怖を描く。
これが小説の極意だ」と言う(なるほど)。
芥川賞と直木賞の違いは、素人にはわからないが、 「芥川賞が、高校野球なのに対し、直木賞はプロ野球の新人王よりも レベルの高いものになっている」とのこと。 |
| - | w008 | 書く力
齋藤 孝 |
著者は、文章の質を上げるには「質を上げてから量に向かうのではなく、 量をこなすことで質を上げると考えよう」と言っている。「原稿用紙十枚を書くトレーニン グを積んでいけば、文章の質は必ず向上する」とのこと。 |
| - | w007 | 日経新聞書評
「64(ロクヨン)」 横山秀夫 |
著者は1957年生まれである。7年ぶりの新作ということだが、 その間廃業を考えた時期もあったようだ。記事に書かれていない苦労が気になる。 書くことを生業とする大変さが隠れているのではないか。 |
| - | w006 | 読ませる技術
山口文憲 |
「ウソを書いてもいいんですか?」に対して、「もちろん、 そんなことはあなたの自由です。必要ならウソもついてください、作り話もして ください。読者からすれば、つまらない本当の話より、面白いウソ話を読むほう がずっとしあわせです」と割り切っている。 |
| - | w005 | 小さな文章
村上玄一 |
作者は、「文章の基本の第一歩は、知っていることを書くということだ。 しかし、誰もが知っていることを書いても、その文章には、さほどの意味はない。 人に読ませるための文章には、読み手の心を動かす工夫が必要である。その一つの方法は、 人の知らないことを書くことだ。」――何気ない著者の言い方だが、辛辣だ。 |
| - | w004 | 小説ほど面白いものはない
山崎豊子 |
「白い巨塔」の山崎豊子でさえ、「名前のわりに所得が少なすぎる」と洩らす。 「私が書きたいものを書く」世界の厳しさが伝わってくる。 |
| - | w003 | すぐ稼げる文章術
日垣 隆 |
作者は、「文章を書くということは、謎解きと同じ」と言っています。
謎解きを文章にする――なるほど。 |
| - | w002 | 名文を書かない文章講座
村田喜代子 |
何度も読み返して、学び直したい本。
著者は、「人間ドラマの葛藤要因は、古今の小説、演劇を含めても、五、六十種しかないという。 たったそれだけの数の中に、この世の愛別離苦、人生のすべての悲喜劇の要素が大別されるというのだ。」 と基本ストーリーの有限性を指摘している。 |
| - | w001 | まず「書いてみる」生活―「読書」だけではもったいない
鷲田 小彌太 |
司馬さんの例をもとに、書くことの意義をわかりやすく書いている。 「楽しむ、たんに時間を浪費するために読書をする。これが読書の神髄だと思う」――鷲田氏は端的に示す。 |